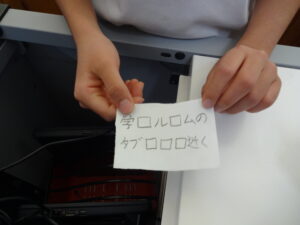今日、5年生で準備してきた学年集会を行いました。
各学級で決めた出し物を、今日に向けて1、2組合同メンバーで準備してきました。
「なぞときゲーム」では、学校内をグループで探し回り、目的となるキーワードを見付けられるよう、グループで相談しながら取り組んでいました。
「協力クイズゲーム」では、たくさんの回答を答える問題や、チームで相談して予想する問題に、グループのみんなで知恵を出し合って回答しました。
集会の目当てであった、「協力」が、様々な場面で発揮されていました。
6年生に向けて、一層みんなで協力する力が高まっています!